平成20年第4回定例会 一般質問内容(詳細)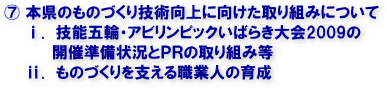 |
||
平成20年第4回定例会 一般質問内容(詳細)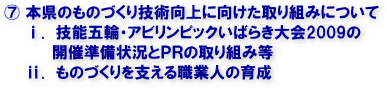 |
||
| 伊沢勝徳 議員 |
|
次に,本県のものづくり技術向上に向けた取り組みについてお伺いいたします。 |
| 細谷 商工労働部長 (答弁) |
| 技能五輪・アビリンピックいばらき大会2009の開催準備状況とPRの取り組み等についてお答えいたします。 まず,大会開催に向けた準備状況とPRの取り組みでございます。 現在,推進協議会のもと,競技対象をおおむね決定いたしまして,競技用の機器類の調達,宿泊施設や輸送手段の確保についても見通しが立ったところでございます。 また,専修学校や実業高校の皆さんにも,ボランティアとして御協力をいただけることになっております。さらに大会出場者や練習にかかる経費の助成等の支援を講じてきました結果,本大会には,これまでの大会を上回る120名を超える選手が参加する見込みとなったところでございます。 一方,多くの県民の方々に会場に足を運び技能に触れていただくことが,本大会の目的の1つでもございます。ホームページでのPR,県内市町村,各種団体,小中学校等へのパンフレットの配布,プレイベントの開催,県内各地の産業祭等でのPR活動等を実施してきているところでございます。今後とも,商工団体,福祉団体等の御協力をいただきなから,効果的な広報を実施してまいりたいと考えております。 次に,大会終了後のフォローでございます。 議員御指摘のとおり,本大会を一過性のものとせず,ものづくり尊重の機運をさらに高め,産業大県いばらきを支える技能者の育成に結びつけることは重要なことであると考えております。このため,小中学生等を対象に,ものづくり体験などを行う出前講座の継続的な実施,産業技術短期大学校や産業技術専門学院における在職者訓練の充実などに加えまして,技術力を有します県内企業の協力をいただき,中小企業の若年者の技能向上を図る新しい仕組みについても検討してまいりたいと考えております。 |
| 伊沢勝徳 議員 |
| 次に,ものづくりを支える職業人の育成についてお伺いいたします。 大学全入時代といわれる今日ではありますが,新規学卒者にする求人状況の変化や求職と求人のミスマッチ,雇用システムの変化といった就職・就業をめぐる環境は大きく変化してきており,一方,若者の勤労観や職業観の未成熟や社会人・職業人としての意識の希薄さといった若者自身の資質の問題も各方面から指摘されております。 少子化などの影響もあり,労働力不足が懸念される中,これは憂慮すべき状況であります。私は,子供や若者たちが夢や希望を持って前向きに自分の将来を考えられるように,そして社会の一員として活躍していくための勤労観や職業観がしっかりと醸成されるような,小中高の段階に応じた組織的・継続的なキャリア教育を推進していくことが重要であると考えます。 特に,ものづくりを支える職業人を目指し工業系の高等学校に入学し若者たちには,実際の職業に直結した,より専門的で具体的な教育がなされなければなりません。 そのためには,現在,県が取り組んでいる企業での職業体験を継続していくことも重要ですが,さらに一歩踏み込んで,企業と学校が相互に連携・協力した実践型の教育を取り入れていくべきだと考えます。 そこで,高等学校において,ものづくりを支える職業人の育成にどのように取り組んでいるのか,また,どのように取り組んでいくのかを教育長にお伺いいたします。 |
| 鈴木 教育長 (答弁) |
| ものづくりを支える職業人の育成についてお答えいたします。 本県では,小中学校においては,働く目的や意義について学ぶために,職場見学や職場体験を実施しており,高等学校ではインターンシップを行うとともに,学校での授業と企業での実習を組み合わせたデュアルシステムによる教育を実施しているところであります。 また,本年度から,小学校から高等学校までの児童生徒が参加し,ものづくり教育の集大成として「いばらきものづくり教育フェア」を開催したところであります。 さらに,議員御提案のように,工業高校においては,企業とのより実践的な連携・協力を進める必要があることから,本年度から県北地域の四つの高等学校を中心として「地域産業担い手育成事業」を始めたところでございます。この事業では,生徒の企業での実習に加え,企業技術者や大学の研究者による学校での生徒への実践的な技術指導,教員の企業等での高度な技術取得,学校と企業との共同研究なども実施しております。 今後は,この「地域産業担い手育成事業」の成果を踏まえ,他の地域にも普及させることにより,地域産業界と一層の連携を深め,ものづくりを支える職業人の育成に努めてまいりたいと考えております。 |
|次の質問へ|1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|新聞記事のページへ|