平成20年第4回定例会 一般質問内容(詳細)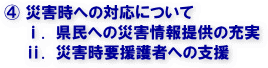 |
||
平成20年第4回定例会 一般質問内容(詳細)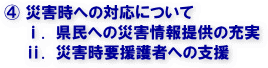 |
||
| 伊沢勝徳 議員 |
|
次に,災害時への対応についてお伺いいたします。 |
| 馬場 生活環境部長 (答弁) |
| 次に,県民への災害情報提供の充実についてお答えいたします。 議員御指摘のとおり,県民に対する的確な災害情報の提供は,社会的混乱を防止し,被災地における県民の適切な判断と行動を助けるためにも大変重要であります。 そのため,現在は県のホームページ上に被害状況や気象情報・地震情報・河川の水位情報などを,茨城県防災・危機管理ポータルサイトとして提供しております。 しかしながら,防災情報システムと連動していないため,別途入力作業が必要であることから,災害時に迅速な情報提供が難しい状況であります。 このため,来年3月の更新に向けて開発を進めております新しい防災情報システムでは,従来のポータルサイトに加え,県のメールサービスに事前登録していただくことにより,携帯電話に直接,避難勧告・避難指示等の避難情報,大雨警報等の気象情報など,最新の情報をリアルタイムで提供できるような機能を導入してまいりたいと考えております。 さらに,このシステムを10月から運用開始しております茨城県域統合型GISと連携させることにより,インターネットを介して,県民だれもが避難所や道路通行どめ,河川の決壊の場所などを地図上で確認できるようにもしたいと考えております。 このように,新しい防災情報システムの開発に当たっては,防災関係機関相互の情報網を再構築することはもちろん,県民が適切に災害に対応できるよう,正確な防災情報の迅速な提供に取り組んでまいります。 |
| 伊沢勝徳 議員 |
| 次に,災害時要援護者への支援についてお伺いいたします。 今申し上げましたとおり,災害発生時には県民への情報提供が大事でありますが,災害情報を把握しにくい方,また,たとえ災害情報を知り得たとしても,身に迫る危険に対して避難など適切な行動をとる面でハンディをお持ちの方がいるのも現実であります。例えば高齢者や障害者,傷病者さらには外国人といった方々であり,こうした「災害時要援護者」への支援が大きな課題でもあります。 例を挙げれば,9年前に東海村で起きたJCO臨界事故では,村の防災無線での呼びかけにも聴覚障害者の方はわからず,24時間以上もたってから事故を知った方々もいたそうであります。 例えば,一見しただけで障害者であることが認識されにくい聴覚障害者の方々には,それをすぐ識別してもらえるような名札やカードを作成・配布し,災害時に瞬時にわかってもらえるような工夫をするなど,要援護者への素早い状況の伝達や避難支援は,その個人個人の状況に応じたきめ細かな対応が求められます。 地域でともに暮らす人々の救助・避難を,その状況に応じいかにきめ細かく迅速に行うかが「災害時犠牲者ゼロ」への大きなかぎでもあり,そのためには個々の要援護者情報を事前に把握しておくことも必要であります。 このため,県内の市町村では,支援が必要な方々を把握するため「災害時要援護者名簿」を作成しているとのことであり,現在44市町村のうち41市町村では名簿を作成済みで,残る3市も名簿作成に向け着手済みだと聞いております。 しかしながら,名簿を作成しただけでは十分ではありません。作成した名簿を最大限に活用し,要援護者一人一人について避難支援者,避難場所,避難方法,情報伝達等を具体的に定めた「避難支援プラン」を県内全市町村において早急に作成しなければなりません。この避難支援プランは各市町村で作成するものでありますが,県として一定の基準を示すことにより,市町村ごとに対応の差がでないよう配慮すべきと考えます。 また,災害に対する日ごろの心構え,意識づけのためにも,支援する側の支援マニュアルだけでなく,支援される側,要援護者用の避難マニュアルを作成し,関係者に配布することも必要ではないでしょうか。さらに,こうしたマニュアルを作成するに当たっては,要援護者が自宅にいるときだけを想定するのではなく,外出時も想定したきめの細かい内容のものでなければならないと考えます。ついては,これらを踏まえ,本県の災害時要援護者支援についてどのように取り組んでいくのか,保健福祉部長にお伺いいたします。 |
| 山口 保健福祉部長 (答弁) |
| 災害時要援護者への支援についてお答えいたします。 県内で約20万人と推計される要援護者を災害から守るために,要援護者名簿の作成や避難支援プランの策定について,市町村の取り組みを支援してまいりました。 その結果,要援護者名簿につきましては,今年度中に全市町村で作成完了の見込みとなっております。 しかしながら,名簿に登録された一人一人について,どのように支援するかを定めた避難支援プランにつきましては,2市で策定を終え,10市町で着手しているものの,まだまだ進んでいない状況でございます。 このため,国のガイドラインに基づき,市町村が取り組みやすく,支援体制に格差が生じることのないよう,早期に県独自の基準を示すなどして,遅くとも平成22年度までに全市町村で策定されるよう働きかけてまいります。 また,要援護者の置かれた状況により,避難の方法も異なりますので,それぞれのケースに対応した避難マニュアルを作成してまいります。作成に当たっては,支援する側,支援される側,双方の意見を十分に反映してまいりたいと考えております。 さらに,毎年行っている防災訓練に,要援護者や支援者の積極的な参加を求め,疑似体験等を通して相互の理解を深め,いざというときの対応について学ぶ機会を提供してまいります。 今後とも,こうした取り組みや高齢者等の見守りを実施している地域ケアシステムの活用を図るとともに,地域福祉の担い手である民生委員との連携を強化し,地域や関係機関が一体となり災害時に一人も見逃さない体制の整備に努めてまいります。 |
|次の質問へ|1 2 3 5 6 7 8 9 10|新聞記事のページへ|