40万ヒット記念 エッセイ
「色情日記」考
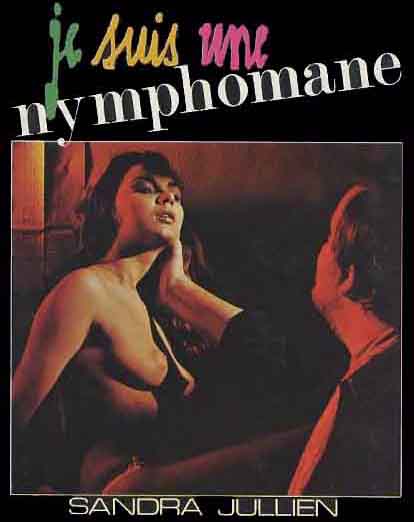
知る人ぞ知る。いや、余り威張って口にするほどの知識でもないだろう。30年ばかり昔のフランスの美人女優でポルノ映画のヒロイン、サンドラ・ジュリアンは上記の題名の映画(‘71)でブレイク、ことに日本で人気が爆発した。招かれて来日し、裸の記者会見で話題をふりまき、2本の映画に主役級で出演(東映「現代ポルノ伝・先天性淫婦」と「色情大名・徳川セックス禁止令」)した。
その後本国で再びポルノ映画(変態白書)に出たけれど、これはたいして受けなかったのだろう。’74年以後はぷっつりと(少なくも日本では)名前を聞かなくなる。私も結構関心があって気になった。
彼女が幸せになったのならそれでよしとしようか。
良く似た例ではまた80年代なかばのAVポルノ界を席巻したトレーシー・ローズ、
 彼女も日本に招聘されて(多分裸の記者会見はなかったはずだが)ヴィデオ作品を残した(「トレーシー・テイクス・トーキョー」)。大人っぽくなっていたトレーシーは、健康そのものの若々しい(デビュー当時、15、6歳、年齢をごまかしていたらしい)豊かな体の張りはなくなっていたけれど、アダルトっぽく綺麗に痩せていて、これも良しと思った。裏版をご賞味されたご仁もおられるだろう。
彼女も日本に招聘されて(多分裸の記者会見はなかったはずだが)ヴィデオ作品を残した(「トレーシー・テイクス・トーキョー」)。大人っぽくなっていたトレーシーは、健康そのものの若々しい(デビュー当時、15、6歳、年齢をごまかしていたらしい)豊かな体の張りはなくなっていたけれど、アダルトっぽく綺麗に痩せていて、これも良しと思った。裏版をご賞味されたご仁もおられるだろう。
彼女は出自こそまったくアンダーグラウンドカルチャー的な存在だったが、サンドラとは異なり、ポルノから足を洗ったあと、ごくまっとう(?)なB級劇場映画で再デヴューしている。
最近自伝が出たようだ(日本語訳はまだ出ていない)。
さて、映画「色情日記」に戻る。確かに、「色情日記」は当時“まっとうな”B級映画ともいえないような位置づけだった。
(題名を見ればおおよその見当がつく。これはAV業界のセンスだといっていいだろう。原題も良く似たものだ “私は色情狂”)
彼女が日本で出演した東映ポルノも、やはりまっとうな映画ではなく、この数年後に大ヒットした同じ仏のポルノ映画「エマニエル夫人」が堂々と一流映画館で上映されたのと比べても、不当なほどの扱いの落差がある。主役のシルビア・クリステルはその後も同種のきわもの映画や、それだけでもない、普通の映画にも出て結構長続きした女優だった。
この3人はそろって日本で人気が出たという。共通点は何だったのだろう。親しみ易さ?日本発のキャラクターに見られる一種の子供っぽさ“かわいい”という特性?
ま、なんでもいい、彼女たちの中では、私はやはりサンドラが好みだ。最も美人だからというのではなく(圧倒的なのはトレーシーだろうか)、演技力がいいというのでももちろんない。日本でのいくつかのエピソードが物語るそのきっぷのよさとともに、早々と銀幕から姿を消した、そのはかなさに気がそそられるというのだろうか。
ま、そんなところは当面置いといて。映画「色情日記」に戻る。
この映画を、まだ独身で若かった私は確か劇場で観た。そのころはヴィデオのような便利なものはなかったから、劇場へ行くしかなかった。もちろん成人指定の映画館だったはずだ。初々しいサンドラのヌードに感激した記憶がある。
30数年後の今年、またこの作品を観る機会があった。どんな経緯で観ることになったのか、それを説明する気分にはないけれど、多分「ノーカット・ヘア解禁版」という惹句に惹かれたのだろう、ということにしておこう。
この小文はその感想のようなものだ。昔の記憶はかなり薄れていたし、新鮮なエロチシズムといったものを期待していなかったわけでもないけれど、最近の国産のAVの内容に比べれば、ポルノとしての濃密さに関するかぎり、あほらしいほどあっさりしたものだろうことは見る前から見当がついたし、さほど期待してはいなかった。
事実、そうだった。
しかし、再見した印象として、(案外)映画作品としてはしっかりしたものだったし、そのストーリーについても、あほらしいというようなものではなかった。これは意外だった。一般的な意味で秀作、とまではいかなかったけれど、さまざま考えさせられた作品だったことは確かだ。この小文はそのサプライズが書かせた印象記なのである。
南仏の小さな港町、フランス海軍の艦長までした退役軍人のお堅い父親とそれにかしづく古風な母親を持つキャロル(サンドラ・ジュリアン)はその家風を反映して許婚者もいるけれど、なおヴァージンを大事に守り続けている清純な娘だった。しかし不幸なアクシデント(エレベーター事故、“転落!”による心身のショック)によって“性の欲情”を強く覚える体になってしまう。彼女に惹かれていた職場の上司、社長の甥がその変化をめざとく利用して悪戯をしかけ、それが発覚し、会社にいられなくなり、田舎のこととて体面を気遣うお堅い家族からも見放され、単身家を出てパリの知り合いが経営するオートクチュールの店に預けられる。その店の女主人は彼女の魅力とその性癖を見抜き、レズの相手に引き込み、更に男友達と一緒になって玩弄を尽くす。刺激の多い生活になお性癖を悪化させるキャロルは夜な夜な男漁りに街をうろつくが、後ろめたい感情との間で悩み続ける。
小旅行の途中に行き暮れて迷い込んだ遊具置き場で出会った職人風の男二人との幻想的なレイプシーンの後、担ぎ込まれた病院で治療を担当した医師にその心的な立場と病理を理解され、その医師の愛情を得たこともあり、彼女は立ち直ることが出来る。
こう書いてみると、筋書きに関しても、どうもまっとうでシリアスな若者の青春劇映画としか思えないのではないだろうか。つまり、例えば、この女主人公を同じ世代の男女を入れ替えて、若い男に、青年にしてみれば、これはより明確になる。男であれ、女であれ若者が性の衝動に悩まされるのはごく普通の風景なのだ。これを殊更にポルノと名打って宣伝これ努めた関係者は、何を見せる積りだったのだろう。いや、私は怒っているのではない。マックス・ペガス監督の狙いは間違いなくポルノにあったのだろう。主人公を若い男ではなく、若い清純な美女に設定したところが(当然ながら)みそだったのだ。
もちろん、従来、文学作品でも性の衝動に悩むのは男に決まっていて、そんな美女の悩む姿を描いたシリアスな映画はなかった(はずだ)。
なぜ誰も考えなかったのだろうか。
それは忌まわしいことだった。つまり、誰も”考えたくもないこと”だったのだ。
若い、美しい女は、ただ清純で、貞節であるはずだという観念。そして、その対極、男にたいして顕に欲情をあらわし、行動に示さずにはいられない率直な女は悪い女、汚れた、罪の女だという思想が一般だった。彼女たちにはただひとつの呼称「売春婦」という不名誉な名前があった。
一般に、それを生業にする女をそう呼ぶけれど、ただ性欲をむきだしにして男を誘う女をそのように称したこともあったのだ。いや、それだけにとどまらず、女という性をその看板にして生きるひとびと、踊り子、酌婦、女優、更には神殿の巫女たちすらも娼婦とされた時代もあったのである。
その昔、いや、つい先の世紀まで、女性は男性のサーヴィスをするためにのみ生まれた階級であると定義づけられた社会、時代があった。女性にとっての暗黒時代。そこでの“常識”として、性欲は男性にのみ存在し、女性にはない、とも考えられていたらしい。つまり、妻として、子供を生み、育てるだけの存在である女。そこにしかまっとうな地位のなかった女たちにとって、不幸にしてその地位が得られなかった、または一度は得たものの様々な原因からそれを失ってしまった、そんな女たちが男性優位の社会に一人で生きるためには、非常に限られた職業しか選べなかった。そのひとつが売春だった。
彼女たちが特別性欲の強い種類の人間だったというわけではない(進んでその世界に飛び込んだ極めて稀な女性たち<まったく居なかったというわけでもないだろう>を別にして)。ただ、不幸な運命に出遭うことになったということだ。しかし、その職業としての必然から、嫌でも男を誘わねばならない、そんな外見の形態が彼女たちを特別性欲の強い人種であろうという見方をされるようになったのだろう。実際は、まったくその逆だったことも考えられる。日々を傲慢な客と接する間に男性不信が一般となり、やがては不感症になる女が多数だっただろうことは想像できる。
しかし、それ(売春婦)は、世の男性たちにとっても特別な存在だった。アンヴィバレンツ、好悪の感情をほぼ同量もち、魅力を感じつつも、また嫌悪の気分も排除できない。ポルノという言葉の語源が、売春についてのの記述一般(の書)によるという事実がそれを暗に物語っている。
けれど、売春婦はさておいても、その実質の暗いネガは、性欲に振り回される女はやはり存在したはずだ。そして、やはりある意味、男性たちにとってその思いつきは興味深いことには違いなかっただろう。(もちろん、当の女性たちにとっても<不幸かどうかは別にして>深刻な問題であるはずだったけれど)そして、結局、フランス映画業界はそれをポルノとして描くことにしてしまった。けれど、私には、その結果、ペガス監督が意図していなかった別のものが“表現されてしまった”ように思ったのだ。
女は貞淑であるべし、という旧弊の常識(現在の日本にも多少はあるはずだ)のなかで育ったキャロルは、自分が強い性欲を持つようになったことに当惑し、強い恥じらいを持ち、それを隠そうとする。病院で医者に相談しようとするが、友人の悩みとして、自分が当の患者であることもとうとう言い出せない。しかし、そんな意思も体のなかからつきあげる性の欲情に打ち負かされ、オナニーに耽り、自ら恋人に迫り、職場ではかねて目をつけられていた好色な上司に誘われれば簡単に身を任せてしまう。失意と汚辱から逃れていったパリでも生活はさらに乱れ、同性愛者に応じ、グループセックスに参加し、夜な夜な刺激を求めて街に出、裸にマントを羽織っただけで徘徊する。気に入った若い男に誘いかける。

若い女がこんな状態では、やはり病気としかいいようがないのだろうか。いや、それは病気ではなかったのではないか。もちろん性欲の強さは男女問わず、ずいぶん個人差が大きいとされる。
男にも淡白なものもいれば、若い女とみれば声を掛けずにはいられない多情な若者(年齢にかかわらず)も少なくない。都会の盛り場を夜な夜な刺激を求めてうろつく多くの男女は現代の普通の風俗にすらなっているといってよい。キャロルは病気ではなく、多少とも性欲の強い、現代の女性だったとしても差し支えないのではないだろうか。しかし、もともと貞淑な彼女はそのことを異常と感じ、悩み、宗教にも救いを求め、結局真摯な異性の愛情を得て心身ともに救われる。これはまことに納得のいく解決なのだが。
もちろん、「色情日記」が上演された‘71あたりは ’05 の現代とは違うかもしれない。しかし、性の風俗としては随分異なってはいても、盛り場をうろつくひとたちの性欲そのものは余り変わっては居ないだろう。パリと東京、フランスと日本で違いはあるかもしれないけれど、それも保守的なカソリック文化の支配するフランスの片田舎と当時のパリとの差ほどもないだろうことは想像がつく。変わっているとしたら、夜の盛り場での主役が男ばかりだったのが、女がそこに混じっても違和感がなくなったということだろうか。もちろんもてなし役としてでなく、一緒になって娯しもうというキャロルのような立場の女たち。
確かにこの映画でサンドラのヌードシーンは少なくはない。セクシャルで魅力的な場面もいくつもある。しかし、私の目には、それらは劇の進行のために必要不可欠なものばかりであり、煽情効果を狙ったことではあっても、行過ぎたものではなかった。この映画がポルノグラフィーとして企画され、その方向で客の動員を狙って、しかも大成功したことは間違いないことではあるけれど、それはただ、サンドラという女優が特別魅力的だったということにほとんど負っていることは間違いないだろう。
何にせよ、彼女が「私は色情狂なの…」と恥ずかしげに打ち明けるのを想像しても、私の返事はやはり「どうだろうか?君が色情狂であることは留保しても、‘05年のインターネットのコンテンツの多くが、そしてそれらを享受している世界中の男女が色情狂そのものだということは請合ってもいいよ。」ということになるのだろう。もちろん、不肖私のこのあやしいサイトも当然それらに含まれるのだろう。
この項 終わり ’05.4.22
アマゾニア 評論集 へ戻る
妄呟舘あまぞにあ HPへ戻る
物語舘アマゾニア HP へ戻る
 since '05.6/05
since '05.6/05
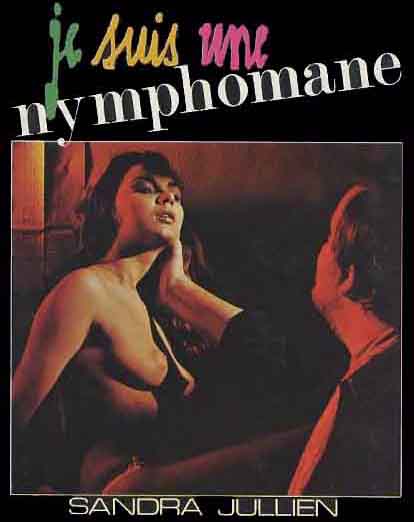
 彼女も日本に招聘されて(多分裸の記者会見はなかったはずだが)ヴィデオ作品を残した(「トレーシー・テイクス・トーキョー」)。大人っぽくなっていたトレーシーは、健康そのものの若々しい(デビュー当時、15、6歳、年齢をごまかしていたらしい)豊かな体の張りはなくなっていたけれど、アダルトっぽく綺麗に痩せていて、これも良しと思った。裏版をご賞味されたご仁もおられるだろう。
彼女も日本に招聘されて(多分裸の記者会見はなかったはずだが)ヴィデオ作品を残した(「トレーシー・テイクス・トーキョー」)。大人っぽくなっていたトレーシーは、健康そのものの若々しい(デビュー当時、15、6歳、年齢をごまかしていたらしい)豊かな体の張りはなくなっていたけれど、アダルトっぽく綺麗に痩せていて、これも良しと思った。裏版をご賞味されたご仁もおられるだろう。