(1-b)有棹撥弦楽器
ネックを持つ撥弦楽器をこのように呼び、リュートやギターがその代表です。有棹でない撥弦楽器にはハープやチター等がありますが,あまり詳しくないので割愛します。
・リュート族の楽器(リュート、テオルボ、キタローネなど)
| ルネッサンスリュート |
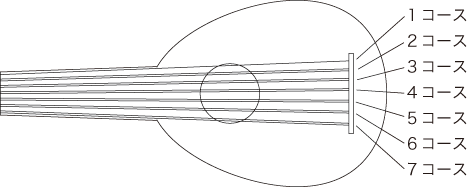 リュートの起源はアラビアで、民族楽器「ウード」が紀元前8世紀頃にヨーロッパに伝わって発展していったといわれています。現在のギターと異なり、基本的に高音弦をのぞいて2本1対で張られており、混乱を避けるため、「1弦、2弦・・・」ではなく、「1コース、2コース・・・」と数えます。 現在でも(かろうじて)使われている最も古いリュートは「中世リュート」で、5コースまでありました。ルネッサンス期に入ると、6コースの「ルネッサンスリュート」が誕生しました。レパートリーにおいても、J.ダウランドなどの大作曲家が現れ、リュート音楽の全盛期を迎えます。現在、単に「リュート」といえば、このルネッサンスリュートを指します。この頃の有名人といえば「ガリレオ・ガリレイ」や「シェークスピア」「レオナルド・ダ・ビンチ」などがいますが、彼らは皆リュート弾きでした。この時代の紳士の条件は「詩が書けて、歌が歌えて、リュートが弾けること」だったそうです。
リュートの起源はアラビアで、民族楽器「ウード」が紀元前8世紀頃にヨーロッパに伝わって発展していったといわれています。現在のギターと異なり、基本的に高音弦をのぞいて2本1対で張られており、混乱を避けるため、「1弦、2弦・・・」ではなく、「1コース、2コース・・・」と数えます。 現在でも(かろうじて)使われている最も古いリュートは「中世リュート」で、5コースまでありました。ルネッサンス期に入ると、6コースの「ルネッサンスリュート」が誕生しました。レパートリーにおいても、J.ダウランドなどの大作曲家が現れ、リュート音楽の全盛期を迎えます。現在、単に「リュート」といえば、このルネッサンスリュートを指します。この頃の有名人といえば「ガリレオ・ガリレイ」や「シェークスピア」「レオナルド・ダ・ビンチ」などがいますが、彼らは皆リュート弾きでした。この時代の紳士の条件は「詩が書けて、歌が歌えて、リュートが弾けること」だったそうです。
| バロックリュート | アーチリュート |
他方、4度調弦のままで、サイズが大型化したものに「テオルボ」「アーチリュート」「キタローネ」というグループがあります(「テオルボ」という名称はこれらの総称としても用いられます)。これらは主に通奏低音用として用いられ、弦数はじつに14コースに達しました。「アーチリュート」はイタリアで用いられ、「キタローネ」は全長2メートルを超える金属弦をもった楽器を指したようですが、これら3種類は当時からしばしば混同されていたようです。カッチーニなど多くのバロック初期の歌曲は、現在ではチェンバロやピアノで伴奏するのが普通ですが、これらのリュートで伴奏するのが本来の姿のようです。
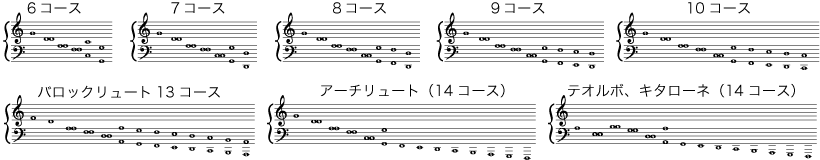
・ギターの仲間
ギターはスペイン周辺で発達した楽器で、リュートによく似ていますが、同じ起源を持つかどうかは定かではありません。エジプトが起源だと言われ、一般に別族の楽器とされています。
| ビウエラ |
 |
|
バロックギター
Anthony Baines著 Europian and American Musical instrumentsより引用 |
古典期に入ると、リュートなどが廃れたのに対し、ギターは引き続き発展していきました。弦はこの頃から1本ずつの単弦となり、低音に1本増えて現在と同じ6弦となりました。また、この頃からロマン派初期にかけて多数の優れたギター音楽作曲家が出現し、「ギターの黄金期」を迎えました。この頃のギターは「19世紀ギター」とよばれ、現在よりも小ぶりで弦の張力も弱いのが特徴です。現在の形となったのは、19世紀の末、すなわち、ほんの100年余り前のことです。