カトリック仙台司教区第1地区青森市内教会のホームページ
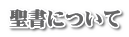 ICS
ICS
NEWS「聖書とはなにか」
- 聖書に向き合う心構えと基本的知識 -
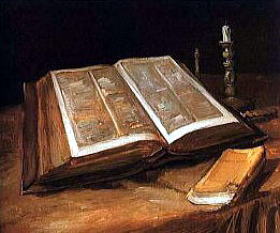
1.聖書という本
(1)聖書に向き合う心構え
①聖書は誰のために何を書き記した本なのか
聖書は神の存在を大前提として、神を信じる者たちと神の救いを求める者たちのために書き記された「信仰の書」です。そして、聖書とは神の存在を証明するために書かれた本ではなく、神の存在を大前提として、神を信じない者たちではなく、神を信じ求める者たちのために、「神による救いの出来事を宣べ伝えるため」に書かれた本です。よって、聖書を読み解くためには、「神を信じる」という信仰がどうしても必要とされます。
また、聖書は「出来事を書き記した本」ですが、歴史的に起きた事実をただ客観的に叙述したのではなく、それらの事実の背後に込められた神の顕現や働き、そして神を信じ救いを求める者たちへの神のメッセージを、詩や戯曲および書簡(手紙)などのさまざまな文学的技法や一定の形式を用いて記している書物です。
さらに、聖書は事実をとおして語られた「神の救いの出来事」を宣べ伝え、神を信じ求める者たちが、それらを「聞いて、信じて、呼び求めて、救われる」ために書き記された書物ですから、聖書とは哲学や倫理の本でもないということです。
よって、聖書とは客観的な史実を叙述した「歴史書」でもなければ、哲学の本でも倫理の本でもないということが言えます。
以上のことをしっかりと踏まえて聖書を読むのでなければ、聖書の叙述を正しく理解し読み解くことはできないでしょう。
②聖書は一定の目的と対象のために書かれている
聖書は、それぞれの聖書記者の霊感により啓示を受け止め、それぞれ明確な意図や目的を持って一定の人々に向けられて書き記された書物です。よって、その時々の時代背景や出来事を踏まえながら読まなければなりません。また、聖書の記事をそのまま現代にスライドさせるのも相応しいとは言えませんし、自分なりの理解や経験で解釈することも、聖書を独断と偏見で読むことにつながる危険性があります。
よって、聖書を正しく読み解くにはそれぞれの文書が書かれた歴史的背景や当時の宗教観や慣習などの文化、そしてどんな出来事があったのかを学ぶことがどうしても不可欠なこととして求められます。
聖書とは、それぞれの聖書記者たちの意図するところの神の啓示や福音等のメッセージを、特定の対象者(民族・共同体・個人等)にあてて書かれた信仰の書ですから、その記事の云(い)わんとするところを的確に捉えるのでなければ、それらを正しく受け取ることはできませんし、結果としてそれでは聖書を読んだことにはなりません。
以上の事柄が聖書を読む心構えとしての大原則です。
③聖書が書かれた時代と現代の自然観・価値観の相違(コンテキスト=文脈やテキストの背景となっているものの重要性)
聖書、特に旧約文書に至っては約二千年以上前に書かれた本ですから、現代の私たちの自然観や世界観とは全くといっていいほどの相違があります。科学技術や知識が普及した現代の私たちは、さまざまな自然現象や事実を科学的に捉えることが常識となっていますが、聖書が叙述された当時の人々はそうではありません。ですから聖書を読み解く際にも、その自然観や世界観の差異を勘案して理解することが大切です。特に聖書が語る奇跡物語の理解には、その物語が語る真意を受け取るのでなければ、ただの信じ難い出来事や笑い話でしかなくなってしまうどころか、信仰の躓きにもなりかねません。
確かに聖書の無(む)謬(びゆう)性(せい)(誤りがないこと)は揺るぎない真実ですが、それは、それぞれの記事が語る神の啓示や福音等のメッセージの真意という観点においてのものです。もし聖書を一字一句、ありのままに現象的な事実として理解する原理主義的な読み方をするならば、他宗教や他教派あるいは他者を排除する独善や独断と偏見、ひいては戦争や紛争、人種・民族差別などの対立をもたらす大きな危険性をはらむことにつながりかねないのです。
人間は多様なものとして神が創造しました。聖書が書かれた時代の自然観や価値観と現代の私たちのそれらを擦り合わせながら、人間の多様性を認めつつ、聖書が叙述する神の啓示や福音のメッセージを受け取るようにしていきましょう。
④聖書に禁止令や信仰に関する義務的勧めが多い理由
聖書文書には旧約・新約ともに、多くの禁止令や信仰に関する義務的勧めの言葉が多く記されています。その理由の主なものは、旧約においてはイスラエル民族のアイデンティティともいえるべきユダヤ教信仰が、律法を守ることで神ヤハウェの救いや恵みに与れるということと、神ヤハウェとの契約であるイスラエル民族の安住の土地と未来永劫に渡る繁栄は、神に選ばれた民族の結束が何よりも重要であったからです。そのために、神ヤハウェに対する信仰が揺るぎないものにすることが最も大切なことであったことは、彼らの民族的・宗教的歴史の中で、信仰が揺らぐことで民族が分裂し、王国が崩壊し、バビロンに捕囚され、ユダヤの人々が離散していくなどの苦い経験から嫌と言うほど思い知らされていたことによるものです。
また、新約聖書におけるその理由は、イエスの死と復活後、弟子たちによる宣教活動によりイエスを信じ信仰するものが徐々に増え教会共同体が形成されていくにつれ、キリスト教信仰解釈が混乱し始めて行きます。とくに、原始キリスト教教会におけるグノーシス派の教えが教会共同体の信仰を混乱させました。そこで、パウロなどの使徒たちは、このグノーシス派の教えに反駁することを余儀なくされたのです。さらに、ローマ帝国によるキリスト者への迫害は凄まじいものがあり、イエス・キリストに対する信仰と教会共同体の維持・継承には、教会共同体内の信仰を揺るぎないものにすることが、必要不可欠なことでした。
四福音書やパウロの書簡とその他の手紙、そして黙示録の全ての新約文書は、それらの目的のために書かれたものですから、どうしても多くの倫理的・道徳的禁止令や信仰に関する義務的勧めの言葉を記すことは避けられないことだったのです。
しかし、新約聖書の核心は、倫理的・道徳的禁止令や信仰に関する義務的勧めの言葉にあるのではなく、あくまでもイエス・キリストの福音にあることは言うまでもありません。そのことを忘れてしまうのであれば、新約聖書をただの禁止令や信仰的勧めの言葉を集め記した律法の書として解釈してしまうことになるでしょう。
このような観点においても、聖書をいかに正しく読み解き、理解するかの重要性があります。
⑤聖書朗読にあたって
上述(1.(1)②)したことからお分かりのように、聖書は一定の目的や意図を持って、信じる者のためにという共通性はありますが、特定の対象の人々のために書かれた本です。ですから、自分なりの理解や経験で個人的に解釈してはならない書物です。
このことから、聖書朗読は、司祭や助祭と同じく、原始キリスト教時代から聖書朗読奉仕者という固定した役割がありました。そして、前述のことを聖書朗読に反映させるために、Lecture
tone(レクチャー・トーン=説教調子)で朗読することが勧められています。もともと「聖なる読書(レクチオ・ヂビナ=Lectio Dibina)」である聖書は黙読ではなく、声を出して音読するのが習慣でしたが、その読み方がレクチャートーンによるものでした。この読み方は、聖書の伝統的な読み方で、個人的な読み 方を廃したや、一般的な物語調や朗読調でもなければアナウンス調でもない、ミサ典礼の中での司祭の語調や主の祈りなどの祈りの語調やリズムにも通ずる聖書朗読独特の調子の読み方です。
聖書朗読奉仕者には向き不向きはあるようですが、適切な指導者や司祭から指導を受け練習していくことで身に付くものです。聖書朗読の最大の目的である聖書を聴衆に読み聞かせるということを具現するためには、最も相応しい読み方でしょう。
2.『聖書』=「BIBLE」の語源
ユダヤ教、キリスト教の聖典であるの語源は、「ビュブロス(ギリシャ語:Βύβλος、ラテン文字表記:Byblos)」にあります。
「ビブロス」は、レバノンの首都であるベイルートの北方約30kmにある地中海沿岸の都市で、古代にはフェニキア人の都市として栄えました。「ビブロス」はギリシャ人 がつけた呼び名で、本来は「グブラ」のちに「ゲバル」。現在はジュベイル(Jbeil)と 呼ばれています。遺跡群はユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。
「ビブロス」は、フェニキア人の発祥の地として有名であり、アルファベットの元になったフェニキア文字もこの地で生まれました。このことからアルファベット発祥の地 と言われることもあります。紀元前3千年紀の前半には、守護神であるバアラト・ゲバ ルを祀った神殿が発見されており、フェニキア人が居住し始めたと言われています。フ ェニキア人は、ビブロスの東に位置するレバノン山脈に自生するレバノン杉を資源とし て活用しました。レバノン杉は船や建築物の資材として適しており、樹脂も利用された。フェニキア人はビブロスからレバノン杉をエジプトへ輸出し、地中海貿易の主役へと躍 り出しました。
「ビブロス」という呼称は、ギリシャ語でパピルス(παπνρος パピュロス) を意味するもう一つの語「ビュブロス(βύβλος)」 に由来するといわれる。「ビュ ブロス」は、紙の原料となるパピルスの茎の内皮を指す「ビュブロス」の指小辞「ビブ リオン」に由来し、小冊子や書物の一部という普通名詞でした。これは、「ビブロス」 が長い間エジプトの支配下にあり、当地の港からエジプトにレバノン杉材が輸出され、その代価としてパピルスなどが輸入され、さらにそのパピルスがこの都市を経由してギリシャなどに運ばれていたので、ギリシャでは紙は原産地のエジプトではなく、積出港の「ビブロス」として知らました。やがてパピルスを意味する「ビブロス」から「ビブリオン(βιβλιον=パピロスの一片=紙本)」という言葉ができ、さらに「ビブ リオン」の複数形である「ビブリア(βιβλια)」から「ビブリオ(βιβλιο= 書物)」の語が生まれ、「ビブル」(聖書)の語が生まれました。
聖書とはもともと「本の集まり」という意味であり、キリスト教会において固有名詞化し、5世紀ごろから聖書全体がビブリアと呼ばれるようになったのです。
また、旧約聖書と新約聖書をそれぞれ英語で、“Old Testament”“New Testament”と 呼びますが、語源はラテン語の「テスタメントゥム」で、遺言という意味である。「遺 言」とは、この世を去る人が、残される次の世代の人に託す「証言」のことです。では 何を「証言」しているのでしょうか。それは神と人間の間に交わされた契約(約束)である。そして、「旧約」とは「旧い契約」、「新約」とは「新しい契約」をさしている。この旧約・新約という呼び方は、まず中国でそう呼ばれるようになり、漢文の聖書を通じて日本でも使われるようになりました。
3.聖書とはどのような書物なのか
(1)聖書の全体像
「わたしの仕えているイスラエルの神,主は生きておられる」(王上 17:1)。エリヤ物語の初めに見られるこの言葉は、聖書の全内容を表している。聖書は、神と人間との 歴史における出会いの物語です。この体験物語は、東地中海の諸国を舞台に、アブラハムとその子孫を中心に展開し、千有余年に及びます。唯一神への信仰は、紀元一世紀の 終わりには、東地中海のあらゆる国に向けられ、多くの民族に、ついに全世界に伝えられることになりました。
必要に応じて、ヘブライ語、アラム語、ギリシア語の三か国語で記されている聖書は、この神体験の集大成です。キリスト教では、これらの文書は旧約聖書と新約聖書の二つにまとめられています。旧約聖書は、アブラハムの子孫であるイスラエル民族と神との 関係を述べています。神は、この民をエジプトでの奴隷状態から解放し、シナイ山で契 約を結び、約束の地カナンを与え、さらにその後の歴史の歩みによって自らを知らせま す。そこには、神による救いの体験に基づいて、未来の決定的救い主を待望させる数々の劇的な物語も織り込まれています。来るべき救い主はメシアと呼ばれ、新約時代にな ると、ユダヤ人以外の人々も、イエスを約束の救い主と信じ、メシアのギリシア語訳で ある「キリスト」の称号をこのイエスに付けることになります。初期キリスト者は、いち早く、イエスこそ、その言葉、行為、死去、復活を通して、神がその民に与えた約束を実現したこと、そして、旧約の預言者エレミヤが告げた新しい契約(エレ 31:31-34)を完成したことを確信するのです。
新約の使徒の一人であるパウロは、「コリントの信徒への手紙2」(3:14)で、イスラエルの指導者モーセを通して結ばれたシナイ山の契約に言及するとき、これを古い契約 と呼んでいます。以来キリスト者は、この契約を中心として書かれた諸書を「旧約聖書」、イエスによる新しい契約を中心として書かれた諸書を「新約聖書」と呼んでいます。新約は旧約に取って替わったとはいえ、新約を理解するためには旧約を知ることがぜひ必要であり、両者は同一の神について語る連続の書なのです。
聖書の神は、その第一ページから、言葉で働く神であり、人間に働きかけます。神はアブラハムに話し、アブラハムは行動に移します。モーセは神の言葉を聞いてエジプト からの脱出を敢行します。イザヤとエレミヤは神の言葉を民に語ります。「ヨハネによ る福音書」は、イエスを神の言葉と呼んでおり(ヨハ 1:1)、事実、イエスには、神が人間に伝えようとすることが余すところなく集められています。聖書の著者はすべて、その名前が知られていると否とにかかわらず、共通して神の言葉の証人であり、彼らのおかげで、今日もこの言葉はわたしたちの生き方を照らし、教え、導き、人々に新しい救いを与えるのです。
EWS旧約聖書の構成と各文書の概要
- 1.旧約聖書の構成
聖書は、旧約聖書と新約聖書に大別できますが、旧約聖書という言い方は、キリスト教からの言い方で、古い契約の意味です。本来、ユダヤ教では「タナッハ(Tanakh)」 (トーラー(Torah)=律法、ネビーイーム(Neviim)=預言書、ケトゥビーム(Ketubim)=諸書からなっています。)と呼びます。
聖書の最初の五つの書トーラー(律法)は、「モーセ五書」と呼ばれますが、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記からなります。新約の福音書でこれらの書は通常「律法」といわれていますが、神の民がシナイ山で結ばれた契約にふさわしく生きるのに必要なことが含まれているからです。
ネビーイーム(預言書)は前後に区分され、前の預言書はヨシュア記、士師記、サムエル記上・下、列王記上・下の4巻で、約束の地カナンに到着してからバビロン捕囚までの歴史が叙述されています。
後の預言書は、大予言書と小預言書に区分されます。大予言書は、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書の3巻で、小預言書はホセア書、ヨエル書、アモス書、オバテア書ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファニア書、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書の13巻で、計15巻からなっています。
ケトゥビーム(諸書)は、ヨブ記、詩編、箴言、ルツ記、雅歌、コヘレトの言葉、哀歌、エステル記、ダニエル記、エズラ記、ネヘミヤ記、歴代誌上・下の12巻からなり、歴史的な記述を含めて、神の賛美や人生訓などが詩歌の形式で書かれています。
ここで律法主義的なユダヤ教の成立に触れておきます。
捕囚から解放されてエルサレムに戻った人々は、預言者ハガイ(ハガイ書)や預言者ゼカリア(ゼカリア書)の言葉に動かされて、紀元前515年に神殿再建を成し遂げています。しかし、イスラエルがかつての栄光を取り戻すことはありませんでした。むしろペルシア帝国による支配は盤石であり、人々は恒常的といえる飢饉すれすれの生活に悩まされ、神への熱心さは影を潜め、自己中心的な生き方に傾いていきました。
そこで、紀元前5世紀の中頃、ペルシア宮殿に仕えていたエズラ(エズラ記)とネヘミヤ(ネヘミヤ記)がエルサレムに帰国し、律法を中心とする共同体の再生に取り組みました。この頃から律法主義的なユダヤ教が誕生することになります。
2.旧約聖書文書の概要
「創世記」には天地万物、人間、イスラエル民族の起源が述べられており、特に、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの偉大な先祖が紹介されています。
第二の書「出エジプト記」は、その名称が示す通り、イスラエルの民のエジプトからの脱出とシナイ山の契約を述べており、これに続く三書のうちの「レビ記」は、レビ族に託された宗教的、民事的法規を収めたものです。「民数記」は、荒れ野滞在時代の人口調査からその名を得ており、「申命記」は、エジプト脱出と荒れ野滞在中の出来事の意味と、約束の地に入る際に守るべき神の律法を述べながら神への誠実を説く、長い温かい勧告の書です。では、この契約によって求められた生き方が記されています。
モーセ五書に、イスラエルの民の歴史的な体験を物語る文書が続きます。生ける神と人間の出会いは、イスラエルの生活の中で展開したからです。これらの書を読むと、長い歴史の歩みの中で、イスラエルの民が忠実であるときにも、不忠実であるときにも、神どのようにしてその民と共におられたかを知ることができます。
これらの文書は大別して二種類のイスラエル史からできている。一つは「ヨシュア記」「士師記」「サムエル記」「列王記」を含み、もう一つは「歴代誌」「エズラ記」「ネヘミヤ記」から成り立っています。
第一のイスラエル史の中で、「ヨシュア記」は、モーセの後継者であるヨシュアの指導のもとでなされたカナン征服と、イスラエルの十二部族に与えられた土地の分割を述べています。「わたしはモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない」(ヨシュ 1:5)。これが聖書全体の伏線となる本書の主題です。勝利の喜びが各ページに感じられます。
「士師記」では、カナン定着に伴う種々の困難な出来事の中で、イスラエル人の心がカナン住民の礼拝する神々に傾き、しばしば近隣の民に屈服させられた経緯が語られています。この苦難のとき、民は神への不誠実を悔い、神に立ち帰って、その助けを願います。神は民の過ちにもかかわらず、この呼びかけにこたえ、救済者として「士師」を遣わします。神は真に民の“救い主”なのです。
「サムエル記」の上下二巻は、部族の統合がいかになされ、サウルとダビデによる中央集権がいかに形成されたかを物語っています。ここに王朝が成立します。
「列王記」の上下二巻は、王朝の終わるエルサレム没落までを述べています。神の要求を具体的に知らせる預言者が現れるのはこの時期であり、彼らの文書である預言書は旧約聖書の終わりに収められています。
「士師記」における不誠実と悔い改めの物語の直後に、ルツというモアブ人女性の誠実を物語る短編「ルツ記」が挿入されています。その誠実な生涯の結果、彼女は偉大な王ダビデの系図に名を連ねることになります。
第二のイスラエル史の中心点は、エルサレムとその神殿です。
「歴代誌」の上下二巻はダビデとソロモンのもとでの神殿建築と礼拝を述べ、「エズラ記」と「ネヘミヤ記」の両書は、捕囚の身となった民のバビロニアからの帰還、破壊された神殿の捕囚後の再建と、エルサレムのユダヤ人共同体の形成を描いています。
「エステル記」は、捕囚となった一ユダヤ人女性が、ユダヤ人絶滅をたくらむ陰謀をいかに挫折させたかを物語っています。
千有余年の間、神がその民のうちに現存した事実を物語る以上の各書に、知恵文学の諸書が続きます。「ヨブ記」は旧約聖書の最も劇的な書の一つであり、ヨブとその友人との対話形式による長い詩です。苦しむヨブが「利益もないのに、神を敬うだろうか」(1:9)ということが対話の主題であり、それはヨブ一人の問題ではなくて、苦しむ義人すべての問題でもあるのです。
「詩編」は、共同あるいは個人の種々の祈りを収めたもので、賛美の詩、感謝の詩、嘆願の詩等から成っています。あるものは救いの歴史を思いめぐらすものであったり、あるものは神を迎えるための生き方を考えるものであったりします。
「箴言」は、人生のさまざまな状況の中で、神の前での正しい生き方を教える知恵者たちの金言集です。ここに示される賢明な行動のみが人間に有益であるのです。
「コヘレトの言葉」は、死に運命づけられた人間の生の意義について考えた、ある知恵者の書で、主題は「ヘベル(空しい)であるこの世をいかに生き抜くか」です。
「雅歌」は愛の歌を集めたものであり、ユダヤ人もキリスト者も伝統的に、これを神と人間との相互愛の象徴的表現と見ています。
旧約聖書は、預言者の説教の集大成で終わります。預言者とは、神の言葉を語るために神によって呼び出された人々です。
「イザヤ」は、紀元前八世紀の後半、アッシリア帝国の最盛期にエルサレムに遣わされた神の使者であり、王と住民全体を、どんなときも神に信頼し、神に従うように招きます。本書の第二部(40~55章)は、バビロニアに移されたユダヤ人に向けられ、第三部(56~66章)は未来のエルサレムを歌っています。
「エレミヤ」も、エルサレムの住民に語りますが、時代的にはイザヤの一世紀以上後の新バビロニア帝国の初期のことです。エレミヤは民を愛しているが、破局の近いことを告げる孤独の人であり、しばしば迫害されます。彼はエルサレムの陥落と王朝の最後の目撃者です。
「哀歌」は、五つの歌から成り、このエルサレムの滅亡を嘆きます。
「エゼキエル」は、エルサレムの神殿の祭司であり、エレミヤと同時代に活躍します。バビロニアに移され、捕囚の民のもとで使命を果たします。しばしば人の思いも及ばぬ行動と弁舌に走りますが、エルサレムの荒廃を知ると、その説くところは変わり、生存者に慰めと救いの使信を告げます。
「ダニエル」は、バビロニア王の宮廷に仕えているユダヤ人の青年として現れ、迫害の中の信仰者に対し、信仰を堅持し神の最終的勝利を希望するよう促します。
これらの四つの預言書に、他の預言者たちの説教を伝える短い文書が加えられ、十二小預言書と呼ばれます。これらの預言者の中には、イザヤやエレミヤと同時代の人もいます。たとえば前八世紀中ごろ、イスラエル王国の隆盛時代に活躍した「アモス」は、形式的な礼拝と貧者への圧迫を告発します。その後しばらくして現れた「ホセア」は、民に対する神の愛、欺かれた愛を告知します。イザヤと同時代の人「ミカ」も、ユダの住民や、不忠実な民に対して神が起こす訴えを語り、第二のダビデの到来を告げます。「ヨナ書」は、やや趣を異にし、ニネベの住民に悔い改めを迫る預言者ヨナの出会った冒険を物語っています。「ハガイ」と「ゼカリヤ」は、捕囚のイスラエルのバビロニアからの帰還後、神殿の再建に協力しており、「マラキ」は、神の正しい裁きと救いの日が訪れることを告げます。
3.旧約聖書続編の概要
この部分の文書は、一世紀末ユダヤ教で聖書の正典目録を定めるとき受け入れられなかったので、ユダヤ人の聖書には含まれていないが、もともとは、紀元前から紀元後一 世紀までの四世紀の間に成立したユダヤ教の宗教的文書です。「知恵の書」と「マカバイ記2」を除く他の諸書は、まずヘブライ語またはアラム語で記され、パレスチナ以外の地に住んでこれらの言語を解しないユダヤ人のために旧約の他の書と同 様、ギリシア語に訳されたものである。キリスト教では、ギリシア語がいち早く共通語となり、初期キリスト者は、離散のユダヤ人たちの用いた「ギリシア語訳旧約聖書」とともにこれらの続編も受け継いでいます。
これらユダヤ人の宗教的文書は、キリスト教によって我々に伝えられたものですが、キリスト教では四世紀ごろからこの文書について、二つの見解が見られるようになります。すなわち、これは旧約の他の書に劣るとする見方と、同等とする見方です。今日、カトリック教会ではこれに旧約と同等の価値が付され、「第二正典」と呼ばれます。もっとも、「エズラ記(ギリシア語)」「エズラ記(ラテン語)」「マナセの祈り」は、カトリック教会もまた「アポクリファ(ギリシア語のαπόκρυφος=隠されたもの=外典」と呼びます。プロテスタント教会では、なんらかの価値を認める教会もあれば、これらのすべてを全く認めない教会もあり、そこでは「アポクリファ」あるいは「外典」と呼ばれます。本聖書では、この部分全体についてすでに戦前に使用されていた「続編」の用語を採用することにしました。
十九世紀までは、一般に旧約続編も翻訳して出版されていました。カトリックとギリシア正教では旧約の他の書の間に、十六世紀初めの若干のカトリック聖書と多くのプロテスタント聖書では、旧約と新約との中間に、まとめて置かれていました。本聖書は後者の慣例に従っています。(この慣例は、1968年にプロテスタントの聖書協会世界連盟とローマの教皇庁キリスト教一致推進事務局とが共同で公にした「聖書の共同翻訳のための標準原則」が定めているところとも一致します。)
「トビト記」と「ユディト記」は、前述の「ルツ記」や「エステル記」と同じく、困難な状況の中で唯一神にいかに忠実に生きるかを示す民間説話です。「ギリシア語 本文によるエステル記」は、「ヘブライ語のエステル記」にモルデカイやエステルの祈りなど、多少の追加をしたものです。「マカバイ記」の二巻は、それぞれ独立の書であるが、いずれも紀元前二世紀、パレスチナのユダヤ人に対する宗教的な迫害のゆえに起きた闘争を物語っています。
「知恵の書」と「シラ書」は、「箴言」の系統に属し、日常生活と人生問題に指針を与えています。「バルク書」と「エレミヤの手紙」は、預言書に類似した文書で、前者は罪の告白、知恵についての思索、エルサレムの慰めから成っています。後者は偶像崇拝に対する警告です。「ダニエル書補遺」には、アザルヤの祈りと三人の若者の賛歌など、ダニエルを中心人物とする三つの教訓的短編が含まれています。
続編の最後に置かれている「エズラ記(ギリシア語)」「エズラ記(ラテン語)」「マナセの祈り」は、「エズラ記(ラテン語)」を除いて、キリスト教の聖書のギリシア語写本によって伝えられ、いずれもカトリック教会では正典の中に数えられていません。「第三エズラ記」「第四エズラ記」「マナセの祈り」の名称でラテン語聖書の付録として出版されていましたが、聖公会の聖書ではアポクリファに加えられています。
「エズラ記(ギリシア語)」の主題は、ヨシヤ、ゼルバベル、エズラによる礼拝の改革であり、これについての史料を提供しています。「エズラ記(ラテン語)」は、黙示文学に属し、おそらく一世紀末に書かれたと思われ、悪、苦しみ、迫害の問題や、神の裁きを述べています。「マナセの祈り」は、神の赦しを謙虚に乞い求める嘆願で す。
EWS新約聖書の構成と各文書の概要
- 1.新約聖書の文書
新約聖書は、イエス・キリストをとおして神と結ばれた新しい契約の意味で、四福音 書[マタイ福音書・マルコ福音書・ルカ福音書(マタイ・マルコ・ルカは同じ資料をもとに書かれているため並行カ所が多々あり、共観福音書と呼ばれている。)・ヨハネ福音書]と書簡(21の手紙)および黙示録の27文書から構成されています。
「神はかつて預言者たちによって多くのかたちで、また多くのしかたで先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によってわたしたちに語られた。」
「ヘブライ人への手紙」冒頭(1・1- 2)のこの句は、新約聖書全体を巧みに要約しています。アブラハム、モーセ、預言者たちを呼び出し、イスラエルの民の長い歴史を通して自らを知らせた生ける神は、民との完全な出会いを実現し、エレミヤが告げた新しい契約を結ぶため、ついにその独り子を送る。「ヨハネによる福音書」はこの独り子 を紹介して、「わたしを見る者は、わたしを遣わされた方を見るのである。」(ヨハ 12 ・45)というイエスの言葉を伝えています。新約聖書はまさに、イエス・キリストを通 して与えられる神と人間との決定的な出会いと、各人にとってのその意義を物語る書です。
2.福音書
(1) 福音とは
福音(ευαγγέλιον=エウアンゲリオン)は、イエスがもたらした決定的救いの恵みであり、福音書は、このイエスがその短い生涯で行い、教えたことを伝え、イエ スの死と復活を語っています。これは伝記というよりも、イエスによって生きた人々の証言記録です。しかし、この4つの福音書は同じ意図で書かれたものではなく、それぞれが異なった対象者を考慮して書いたものですから、それぞれに相違も特徴 もありますが、その共通点は「イエスが何者であったのか。」を語っていることで す。
それは、初代教会が発展していく中で、信徒の教育も組織化する必要が生じ、そ こでキリストの弟子たちは自分たちが個々に教えていた話や資料[イエス伝や信仰 宣言などの定型文(ケリュグマ)など。]を集め、それらを書き残す仕事を始めま した。それが現在の福音書という形式の元となりました。
(2) 共感福音書
共感福音書は同じ資料(通称Q資料といわれるもので現存したかどうかもはっき りしていない。)とマルコ福音書が元となって書かれたようですが、その内容の骨子は簡単です。まず、「洗礼者ヨハネによるイエスの洗礼」、「イエスの砂漠での断 食」、「ガリラヤでの宣教活動」、「エルサレム入城」、「イエスの逮捕」、「十字架上の 死」、「三日目の復活」というものです。これらをその事柄の起きた順に記すという よりも、むしろ教育的に事柄や言葉を集めて順序づけています。さらに、福音記者 はそれぞれ自分自身の体験や自分で調べたことなどを付け加えたり、反対に自分流 に削除したりもしています。そして、この3つの共感福音書は、多少の前後はあり ますが、イエスの死後50年ぐらいの紀元80年頃までにそれぞれ書き上げられてい ます。
(3) マタイによる福音書
「マタイによる福音書」のマタイは、福音書に出てくる徴税人レビで、イエスの 十二人の1人という説がありますが、はっきりしたことはわかりません。それは、 マタイ福音書のみならず、どの福音書にも記者名が明記されていないからです。
マタイ福音書は、ユダヤ教から改宗したキリスト者に特に留意して編集されています。そのため、ユダヤ人の中にあるいろいろな習慣については説明せず、信徒の信仰教育に重点を置いています。また、イエスの教えが中心となっていますから、 人物やその心情などはほとんど描かず、「イエスは、旧約時代に預言された救い主 であること。」と「イエスの教えは、旧約時代の教えの完成である。五つの大説教 (5 ~7章、10章、13章、18章、24~25章)」という点を主に強調しています。
(4) マルコによる福音書
「マルコによる福音書」のマルコは、十二使徒の筆頭者であるペテロの弟子で、『使徒言行録』に宣教の大使徒パウロとともに宣教旅行をした「マルコ」と同一人 物という説がありますが、福音書の中でイエスを逮捕した群衆の手から裸のままで逃げた若者がマルコ自身であろうと考える人もいます。前述の通りその真偽についてははっきりしていません。
マルコ福音書は、異邦人の改宗者であるローマの信徒を対象としており、そのためにユダヤ人の習慣を説明したり、ラテン語を使うローマ人に分かるように、所々にラテン用語が用いられています。また、マルコはイエスの人柄に重点を置いてい ため、イエスの感情や視線にまで注意を払い、群衆の反応までも細かく描いています。マルコは、そのような表現技法を用いてより生き生きとしたイエス像を描くことで、福音の言葉によって絶えず働いているイエスに従うよう、人々を招いているのです。
(5) ルカによる福音
「ルカによる福音書」のルカは、ギリシア、ローマの高い教養を持った意思であるとされる説もあり、この福音書には、他の福音書よりも医学的な用語や説明が多 く見られます。また、4つの福音書の後にある『使徒言行録』も同一人物によるも ので、いずれもティオフィロ(神を愛する者たち)様宛への献呈本の形を取って書 かれてあります。
ルカ福音書は、ギリシア文化に親しんでいる読者に向けられて書かれており、ユ ダヤ人のみならず、異邦人を含むすべての人々への理解を示し、全人類に及ぶ神の 愛を示しているのが特徴です。また、人の救い主であるイエスが、特に弱い者、小 さい者や罪人に近づいて、これらの人々に福音を語ることが強調され、エルサレムで十字架に掛けられ、復活するためにエルサレムに上るイエスの姿を記し(9:51~ 19:27)、この死と復活の神秘こそ、地の果てまで告げ知らされることが、救いの使 信の核心であると伝えています。もう一つの特徴としては、ルカはすべての資料を 調和的に順序づけるために、重要な出来事はエルサレムを中心に記していることで す。
(6) ヨハネによる福音書
「ヨハネによる福音書」のヨハネは、イエスの愛しておられた弟子で、最後の晩餐においてイエスの胸元に寄りかかって「主よ、裏切るのはだれですか」と言った 弟子が書いた。(ヨハ 21・20-24)とあります。
ヨハネ福音書は、およそ紀元95~100年頃に書かれたものとされ、他の共感福音 書とは異なった視点で書かれています。イエスの言行など外部的なものを主に記してある共感福音書を補って、キリストの内的生活や神である御父との深いつながりに重点が置かれており、この福音書の対象者は、求道者や新しい信徒ではなく、既に相当キリスト教の教えを知っている人々であったと考えられています。
ヨハネは「ヨハネこそ真の神学者」といわれていますが、彼の神学は学術的なものではなく、キリストの言葉を最も深く理解し、それをわかりやすく解明した人で ありました。また、イエスを旧約時代以前の天地創造の時から先在した神の独り子救い主と信じ、生命・光・真理に関する記者独自の見解によって、永遠の命を得るように記され、イエスの言行のうち特に意味深いものを伝えようとしています。
ヨハネ福音書は特に「愛」について語っていますから、「愛の福音書」とも言わ れ、私たちに「互いに愛し合うことが最も大切である」ことを教えています。その 源と父なる神の愛については、「神は、その独り子をお与えになるほどに、世を愛された。…神の子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。」(ヨハネ 3・16-17)と明記しています。
(7) 使徒言行録(新改訳聖書では『使徒の働き』)
「使徒言行録」は、ルカ福音書の著者がその福音書の続きとして書いたもので、ルカ福音書と同じくティオフィロ(神を愛する者たち)様宛への献呈本として書かれていますす。その内容は、教会の初期の状況を述べるような形で、実はそのすべてにおいて働いておられるのがイエス・キリストであり、天の御父とキリストとの霊である聖霊こそが、教会の歩みの中で働いているということを述べようとしています。
そして、ペトロとパウロという二大使徒の働きをそれぞれ前半と後半の中心に置き、この二人の活動を通して、イエスがもたらした救いの告知が、ペトロとパウロなどによってエルサレムに始まり、サマリア、シリア、ギリシアから、ローマまでに広がる経過を描いています。
つまり、この著者は、歴史としての初代教会の言葉を記録しておこうとしたのではなく、使徒の働きを通して、当時の教会共同体の読者に信仰の励ましを与え、何とかしてユダヤ人以外の人々をもキリスト教の信仰へと導こうとして書かれたものなのです。
(8) パウロ書簡
『パウロ書簡』とは使徒パウロの手紙(歴史的キリスト教会がパウロのものとしてき た手紙であり、彼が創設した諸教会、訪ねようと思うローマのキリスト教徒、あるいは彼の協力者にあてられたもので、手紙の配置は、年代順ではない。)の総称です。 近代の高等批評では牧会書簡だけでなく、いくつかのパウロ書簡は単にパウロの名を借りただけのものであると主張され、そのようなものは「擬似パウロ書簡」などと 呼ばれています。一般に高等批評ではパウロ書簡の成立が福音書群に先立つとしています。
パウロの書簡は以下の通りです。
1.ローマの信徒への手紙 (ローマ人への手紙、ローマ書 パウロによる)
2.コリントの信徒への手紙一 (コリント人への手紙一 パウロによる)
3.コリントの信徒への手紙二 (コリント人への手紙二 パウロによる)
4.ガラテヤの信徒への手紙 (ガラテヤ人への手紙、パウロによる)
5.エフェソの信徒への手紙 (エフェソ(エペソ)人への手紙 パウロによる)
6.フィリピの信徒への手紙 (フィリピ(ピリピ)人への手紙 パウロによる)
7.コロサイの信徒への手紙 (コロサイ人への手紙 パウロ)
8.テサロニケの信徒への手紙一 (テサロニケ人への手紙一 パウロによる)
9.テサロニケの信徒への手紙二 (テサロニケ人への手紙二 パウロによる)
10.テモテへの手紙一 (一テモテ (牧会書簡)パウロによる)
11.テモテへの手紙二 (二テモテ(牧会書簡)パウロによる)
12.テトスへの手紙 (テトス書(牧会書簡)パウロによる)
13.フィレモンへの手紙 (ピレモンへの手紙 パウロによる)
14.ヘブライ人への手紙 (ヘブル人への手紙 パウロか?)
⑤パウロの各手紙の主な内容
1.ローマの信徒への手紙
「ローマの信徒への手紙」は、神の恵みの力、罪人である人間の姿、信仰による救い、信仰者の新しい生き方、死んで復活したキリストとの一致、また聖霊による新しい生活等、パウロの説教の重要な主題を扱っています。
2.コリントの信徒への手紙一・二
「コリントの信徒への手紙」は、パウロが一年半滞在して創設したコリントの教会にあてられています。その中の「第一の手紙」は、彼の出発後分裂した共同体を一致させ、提起された諸問題に答えています。よく知られている「愛の賛歌」は13章に記 されています。
「第二の手紙」は、パウロの不在中に反対者が現れたコリント教会の危機時代をかいま見せ、パウロの和解の熱意と和解に続く大きな喜びが知らされます。パウロは本書でエルサレムの教会への献金を勧めていますが、後半の数章(10~12章)はパウロの心を示す自伝的なものです。
3. 「ガラテヤの信徒への手紙」も、異なる信仰の危機への応答であり、パウロは、キリストがもたらした新しい契約の特長を情熱を傾けて語っています。
4. 続く三つの手紙と「フィレモンへの手紙」とは、パウロが牢獄で書いたものです。まず、「エフェソの信徒への手紙」はユダヤ人、異邦人を問わず、キリスト者はすべ てキリストに一致して、キリストの体を形づくっていることを説明したのち後半では、この一致を日常生活の中で生きるように促しています。
5. フィリピはパウロが創設した西洋の最初の教会であり、「フィリピの信徒への手紙」 には援助への感謝が述べられています。パウロは獄中にあっても、キリストによる喜びと信頼とに満たされており、喜びの手紙といわれています。
6. コロサイはエフェソの東方の町で、キリスト教の共同体はパウロの弟子によって創設されました。パウロは「コロサイの信徒への手紙」の中で、種々の宗教思想によって惑わされているキリスト者を助けるために、救いにおけるキリストの卓越した役割を説いています。
7. 「テサロニケの信徒への手紙一」は、パウロの最も初期の手紙で、未熟で迫害にさらされている信者たちを力づけるために書かれています。「第二の手紙」は、キリストの再臨を見られないのでないかとの不安を抱くキリスト者にこたえているものです。
8. 「ヘブライ人への手紙」は、長い勧告の書であり、旧約聖書を引用しながら、キリストが預言者、天使、モーセにまさること、またその祭司職は旧約のそれをはるかに凌駕することを指摘し、よく知られる11章には、信仰のすばらしさが述べられています。本書がどこで、だれにあててしたためられたかは分かっていません。
9.司牧(牧会)書簡
1.テモテへの手紙一
2.テモテへの手紙二
3.テトスへの手紙
牧会書簡とは教会の指導的な立場にあるテモテとテトスに宛てて書かれたテモテへの手紙一、テモテへの手紙二、テトスへの手紙の3つの手紙をいいます。テモテとテトスのこの2人は、いずれも地方の教会の責任者である牧者として働いていた人です。つまり、個人宛の手紙というよりは、実際に各協会を指導し、運営していくための指示や勧め・助言のようなものです。これらの手紙は、18世紀の頃から「司牧(牧会)書簡」と呼ぶようになりました。
「テモテ」と「テトス」はパウロの協力者で、パウロは彼らに託された教会をよく指導するよう励ます三つの手紙(「テモテへの手紙1、2」と「テトスへの手紙」)を送ります。「フィレモン」はパウロの友人、協力者であり、獄中のパウロは、主人のもとか ら逃亡し自分のところでキリスト者となった、フィレモンの奴隷オネシモを兄弟として迎えるよう勧告します。
(6) 公同書簡
公同書簡とは特定の共同体や個人にあてられたものではなく、より広い対象にあてて書かれた書簡という意味です。各々の書物には伝承の著者たちがいるが、近代以降の批 判的研究はそれらが単に使徒の権威を利用するために著者名としてその名を冠したと主張しました。
「ヨハネの手紙2、3」以外は、キリスト者全体にあてられています。「ヤコブの手紙」は、信仰生活の実際的側面、特に共同体内での人間関係や家の問題に指針を与えています。「ペトロの手紙1」は、迫害によって失意のうちにあるキリスト者を勇気づけ、「ペ トロの手紙2」と「ユダの手紙」は、異端に対して信仰を純粋に保つよう求めています。「ヨハネの手紙1」は、キリスト教の本質である愛を語っています。この手紙と「ヨハネの手紙2、3」は、神の子の受肉を否定する説に直面しているキリスト者の信仰を強める目的で書かれています。
公同書簡は以下の通りです。
1.ヤコブの手紙 (ヤコブ書 主の兄弟ヤコブか?)
2.ペトロの手紙一 (一ペトロ ペトロによる)
3.ペトロの手紙二 (二ペトロ ペトロによる)
4.ヨハネの手紙一 (一ヨハネ 使徒ヨハネによる)
5.ヨハネの手紙二 (二ヨハネ 使徒ヨハネによる)
6..ヨハネの手紙三 (三ヨハネ 使徒ヨハネによる)
7.ユダの手紙 (ユダ書 使徒ユダ (タダイ)と主の兄弟ユダの二説があります。)
(7) 黙示文学
ヨハネの黙示録 (ヨハネへの啓示 使徒ヨハネによる)
新約聖書は、人間を救う神の計画が、キリストの輝かしい再臨に向かって、どのように完成されるかを象徴を用いて示す「ヨハネの黙示録」で終わります。これは迫害の下に苦しむキリスト者を励ます書で、新約聖書において唯一の預言書です。
タイトルの「黙示」とはギリシャ語の「アポカリュプシス(古代ギリシア語: Ἀποκάλυψις)」の訳であり、καλύπτω(覆う)に接頭辞のἀπό(離れて)が 組み合わさったἀποκαλύπτω(明かす、明らかにする)という動詞に、-σις という抽象名詞を作る接尾辞が付いた複合語です。よって、本来の意味は、「裏に隠されているものを表に現す」という意味です。英語では「Revelation」と言い、上記と 同義のラテン語revēlātiō(暴露、すっぱ抜き)に由来します。
『黙示録』はキリスト教徒の間でも、その解釈と正典への受け入れをめぐって多く の論議を呼びおこしてきた書物ですが、ヨハネの黙示録は2世紀に書かれたと言われ ているムラトリ正典目録に含まれており、A.D.397年に開催されたカルタゴ会議では、ヨハネの黙示録を含む27 文書が正典として認められました。
「黙示録は」は、その内容からいえば、キリストの教会のこの世における成り行き と、世の終わりのことを述べています。この世ではキリストに反対する悪の力が強く て、キリストの教会は激しく迫害され、多くの人が惑わされる。しかし、ついには神 とその独り子キリストが悪の力に打ち勝って、清く信仰のうちに踏みとどまった人は、キリストの勝利に預かり、神の国の喜びに入ることが許されるという預言が、神秘的な文学的表現によって叙述されています。
参考文献
1.「日本聖書教会HP」 聖書を知る 聖書とは https://www.bible.or.jp/know/know01.html
2.「なぜ聖書は奇跡物語を語るのか」 雨宮 慧 著 教友社
3.「図解雑学旧約聖書」 雨宮 慧 著 ナツメ社
4.「聖書入門-四福音書を読む-」オリエンス宗教研究所 編 オリエンス宗教研究所
5.「初代教会と使徒たちの宣教」 オリエンス宗教研究所 編 オリエンス宗教研究所
6.「イエスとその福音」 岩島 忠彦 著 教友社(聖書を読み解く集い使用テキスト)
7.「岩波キリスト教辞典」 大貫隆・名取四郎・宮本久雄・百瀬文晃 編集 岩波書店
文責
青森県第一地区カトリック本町教会教育部 聖書を読み解く集い 主宰・文責 佐井 総夫