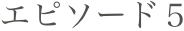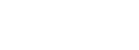今にもまして、幼いころは強情だった。一旦言い出すと、聞き入れてもらえるまで、我を張るのが常で、おまえが泣きだすと恐ろしかったと今でも母に言われる。
ある日のこと、近所の友人の家の窓ガラスが割れていたことがあった。当時、道はまだ舗装されておらず、よく石を投げて遊んでいたのは確かだったが、どういういきさつか私が犯人ではないかと疑われてしまった。私は心外だった。そして怒って、大声で言った。「僕じゃない」と。ところが、ますます怪しいということになってしまった。私はなんとしても身の潔白を晴らさねばならぬと考えた。そこで、一目散にその友人の家へと走り、石を拾い、窓ガラスめがけて投げつけた。「これは僕がやったけど、あれはやってない!」と大声で泣いた。疑いは晴れたが、その後、何かにつけ、この話を持ちだされ、困惑することになった。「おまえは怒らせると何をするかわからないからねぇ〜」と。ぬれぎぬをきせた大人たちが悪いのに、とそのたびに苦々しく思ったものである。
変わって、初恋?の話。幼稚園の年長の時だったと思う。「まりよちゃん」という少しおませ?な子がいた。仲は良かった。告白すると、幼いながらも少なからず意識していたのは確かである。ところがある日の帰り際、このまりよちゃんが何を思ったのか、私のほっぺたにチューをしたのである。今想像するに、きっとTVか何かで見て、真似をしたのだと思う。いくら幼稚園とはいえ、この行動には話題が沸騰した。私の両親にもすぐに伝わって、毎朝、毎晩、「まりよちやん」「まりよちゃん」とからかわれることになってしまった。もう本当にうんざりしたし、「忍ぶに耐え難い」という状況だった。プライドを守るためにまりよちゃんとは絶交し、他の女の子とも絶対に口をきくまいと心に決めた。
この出来事は、その後の人生に少なからぬ影響を与えた。まず、当時通っていた「ヤマハオルガン教室」には全く興味を失った。「音楽は女がするものだ」と思ったからである。「やめさせてくれ」と母に頼んだ。すると話を聞いた父が、「どうしてもやめたいなら、この本の一番最後の曲を弾いてみろ。弾けるようになったらやめさせてやる」と言い放った。
今思えば、初歩の初歩にすぎないような簡単な曲だったが、当時の私にしてみれば、かなり高いハードルだった。が、ここであきらめたら、ずぅっとあの女の子だらけのオルガン教室に通わされることになる。「弾けるようになったら本当にやめさせてくれるのか」「ああやめさせてやる」こんなやりとりのあと、私は特訓を始めた。何としても父の要求にしっかりと応えて、あのオルガン教室をやめようと決心した。何日か後、この曲を父の前で完壁に弾いた。「じゃ、やめさせてくれるよね」「オルガンを弾けるようになったのに本当にやめたいのか」「やめたいから弾けるようにしたんだもん」私の強情が身にしみている両親はこれ以上何も言わなかった。翌月から、私は晴れて自由の身となった。ちなみに、この曲は33年経った今でも弾くことができる。実にばかばかしい。
その後小学生になっても女の子とは親しく口をきくことはなかった。中学を受験するときにも、志望校が、男子校であったことが大きな励みとなった程である。
やがて思春期になって、当然自分の愚かさを後悔したし、今思うと、ゆがんだ女性観を持ち続けたことは、やはりまずかったと感じている。神様のご慈悲か、ご配慮か、今では女性だらけの職場で仕事をしている。なんとも皮肉なものである。
2001年4月発行 院内新聞「まうす」第43号より
v